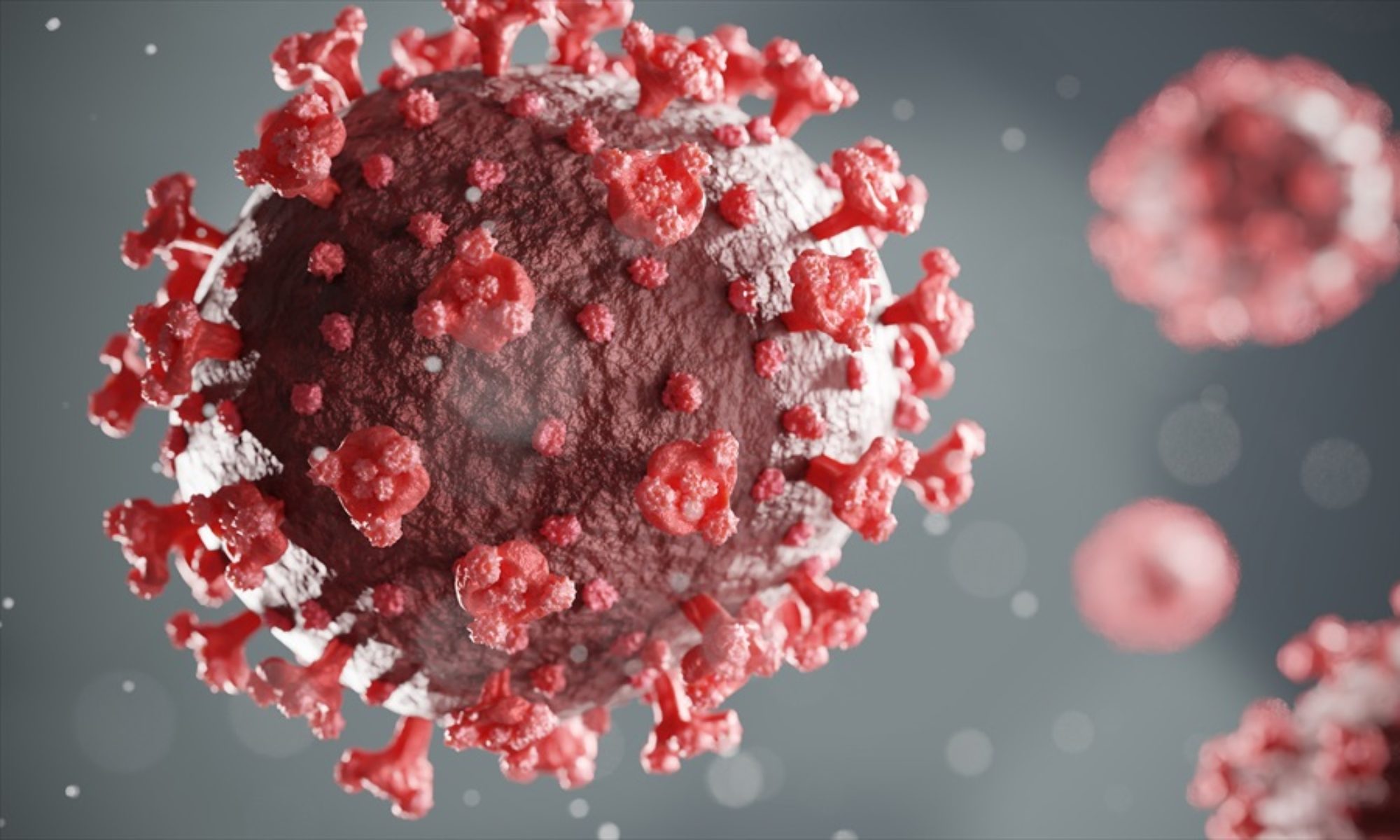-マリヤ・クリニックニュース 2023.1(No.334)より -
新型コロナ対策は、世界中で規制を緩めていますが、これまでの対策が有効であったかどうかのチェックをしなければなりません。
A.現在の新型コロナの感染状況
厚労省の新型コロナの情報https://covid19.mhlw.go.jp/を見ますと(2023.1.16.)、1週間で128,379人の新規陽性者が出ており2022年8月頃と同程度ですが、2022年9月26日から全数届け出から一部の対象者のみの届け出に変わったために、実際にはもっと多くて最多の感染者が出ていると思われます。重症者は確かに減っているのですが、死亡者は過去最高を記録し続けています。死亡者の殆どは60歳以上の高齢者です。それなのに、国も医学界も新型コロナ感染症を2類相当から5類にしようとしています。その理由は、患者や治療を考慮するよりも、経費節減目的が大きいと思われます。治療費が公費で負担されなくなると、感染しても治療を受けられない、受けない可能性が出てきます。
さて、新型コロナワクチンの接種状況は、1回目接種が人口の77.87%、2回目が77.38%、3回目が67.85%、4回目が44.47%、5回目が20.37%と急激に減っています。そのワクチンが原因で死亡したことを国はなかなか認めませんでしたが、否定できないので20人の因果を認めて死亡一時金を支給しました。 ゼロコロナ政策を取ってきた中国政府も殆どの対策を放棄し感染者の発表もしなくなりました。中国のワクチン接種は34億回に達しても期待されるほどの効果がなかったのです。
B.ワクチンは有効だったのか
新潟大学医学部元教授の岡田正彦医師は以下のような見解を出しています。引用が多いので、確認をなさる方は、岡田先生のホームページをご覧ください。
https://okada-masahiko.sakura.ne.jp/
1.インターフェロンについて
「インターフェロン」という言葉を、どこかで聞いたことがあるもしれません。「インフルエンザに感染した際に分泌され、後から侵入してくるウイルスをブロックする物質」として65年ほど前に発見されたものです。「妨げる」という意味の英語(インターフェア)から命名されました。
その後、研究も進み、同類が数十種類もあり、多彩な働きをしていることがわかってきました。中でも大切なのは、「ウイルスの増殖を抑える」、「抗体の産生を促す」、「がん細胞を抑え込む」という3つの働きです。その期待から、これまでウイルス性肝炎や腎臓がんの治療に使われてきました(ただし副作用と効果への疑問から、最近はほとんど使われていない)。
実際にコロナに感染した人の体内では、このインターフェロンが急増します。ウイルスと戦うための物質ですから当然のことです。ところが、なぜか新型コロナワクチンを打った人では、インターフェロンがむしろ低下してしまうことがわかったのです。
インターフェロンがなくなると、まず困るのは「細胞内の異物を見つけ、細胞の表面に提示する役目の免疫物質」が働かなくなってしまうことです。もしそうなら、抗体を作ることができなくなってしまいます。また、ウイルスの増殖を抑える仕組みが働かなくなり、自分と敵を区別することができなくなり、さらに細菌感染症も起きやすくなります。
新型コロナワクチンの副作用として、自己免疫疾患を発症したり、急性腎盂腎炎や蜂窩織炎などの細菌感染症が激増したり、あるいは帯状疱疹などのウイルス性疾患も増えたりすることを当ホームページ(岡田博士のHP)で報告してきましたが、その理由がこれで説明できそうです。インターフェロンが低下すると発がんが促進されることも、すでに多くの研究でわかっていました。
では、なぜワクチンが問題なのか?それは、新型コロナワクチンの主成分であるメッセンジャーRNA(mRNA)には、ヒトの体内で異物として破壊されないよう、さまざまな修飾がなされているからです。そのことが裏目に出てしまい、ワクチンが異物と判断されず、神様の贈り物ともいえるインターフェロンが働かなくなってしまうのです。単に働かないだけでなく、分泌量が普段より減少してしまうのですが、その理由については研究の進展を待ちたいと思います。
2.改造メッセンジャーRNAに毒性がある
「ワクチンのメッセンジャーRNA」は、体内で抗体を作るために新型コロナウイルスの体の一部である「トゲトゲ蛋白」だけを再生する遺伝情報を、試験管内で人工的に組み立てたものです。このまま注射で体内に入れると、ヒトの免疫システムによって異物とみなされ、即座に破壊されてしまうのです。これを避けるためには人工のメッセンジャーRNAをどう改造すればよいのか、が課題でした。30年ほどの奮闘の歴史を経て、改造の技術は一応、完成したとされています。だからこそ新型コロナワクチンは製品化されているわけです。さて、その改造の裏側に潜んでいた重大リスクとは、いったい如何なるものだったのでしょうか?
RNAの遺伝情報はアデニン、グアニン、シトシン、ウラシルと名づけられた4種類の物質で表現され、それぞれ記号でA、G、C、Uと表記されます。ワクチンのメッセンジャーRNAは、改造された部分を中心に、GとCの占める割合が本物のウイルスのそれに比べて異常に高かったのです。以下は、全遺伝情報(A+G+C+U)中に占めるG+Cの割合です。
新型コロナウイルスのmRNA → 36%
ファイザー社ワクチンのmRNA → 53%
モデルナ社ワクチンのmRNA → 61%
特にGの割合が高いほど、4つのグアニン(G)が四角形に並び、それが積み重なって、ちょうど立体駐車場のような形になります。その様子から「G4」と呼ばれるようになりました。G4ができてしまうと、細胞内のタンパク再生工場は、メッセンジャーRNAのコードを解読するスタート点を間違えてしまい、おかしなタンパク質を合成してしまいます。
もうひとつ、重大な発見がありました。トゲトゲ蛋白の遺伝コードの一部が、「プリオン」と呼ばれる危険なタンパク質にそっくりだったのです。「狂牛病」の原因がプリオンでした。
諸々の悪条件が重なり、神経を損傷させるタンパク質や、発がんを促進するタンパク質、そして免疫機能を止めてしまうような様々なタンパク質が作られ、エクソソームとなり別の細胞に運ばれ、神経難病、認知症、がんなどを促進し、さらに免疫機構の破壊も引き起こしているのではないか、と考えられるのです。
現時点では、あくまで仮説です。しかし、ワクチンを接種したあとに悪性リンパ腫が悪化し、PET/CTで検査したところ病巣が5.3倍にも広がっていた患者がいる、との論文発表もあります。DNAやRNAに認められるG4構造は、人類にとって病気の原因となる危険な存在です。そのため、悠久の時間の流れの中で徐々になくなっていくよう、遺伝子の組み換えがなされてきたと考えられています。コロナワクチンは、その自然の摂理を台無しにしてしまったようです。
3.繰り返しのワクチン接種が免疫機能を破壊する?
新型インフルエンザ(H1N1)と呼ばれた感染症が、2009年に大流行したのをご記憶でしょうか。そのとき、1957年生まれの人たち(52歳)を中心に、感染して死亡した人の割合が異常に高くなっていました。この人たちが生まれた1957年は、新型インフルエンザとは別のタイプのインフルエンザ(H2N2)が流行した年でした。H○N○はインフルエンザウイルスの変異を表わす記号ですが、2つの異なる時代に流行したウイルスの間には、互いによく似てはいるものの、少しだけ違うという特徴がありました。
インフルエンザに罹ったことがある人は、免疫がついて、あとで再び感染しても軽くすむはずです。しかし「むしろ致死率が高まった」という、この不思議な逆転現象は、インフルエンザ以外の感染症でも昔から認められていて、一部の免疫学者は、とくにワクチンを作る際に気をつけなければならないと、警告を発していました。研究も進み、その理由が徐々にわかってきました。
ウイルスに対抗する抗体を作る役割を果たしているのが、「B細胞」と呼ばれる免疫細胞です。(B細胞についてはMCニュース2020年8月号をご覧ください。)
抗原と抗体との闘いは、1対1のピンポイントでなければなりません。抗体が手当たりしだい暴れてしまっては、健康な細胞まで傷ついてしまうからです。この選抜の記録は、別の免疫細胞によって、あとまで保存されます。実は、この大切な機能が、免疫システムの最大の弱点でもありました。
ウイルスに最初に感染すると、その記録が免疫細胞に残されますが、あとで少しだけ形の異なるウイルス(変異株)に感染した際、「少しだけ違うこと」を理由に、その抗体を作るB細胞が、過去の記録に従って抹殺されてしまうのです。冒頭に述べた、インフルエンザのH1N1株とH2N2株の関係が、まさにその実例でした。
いま最大の懸念は、新型コロナワクチンで同じことが起こっているのではないか、ということです。ワクチンによって体内の免疫システムに記憶された「抹殺の記録」に従って、少しだけ変異したウイルス(たとえばオミクロン株)に感染すると、その抗体を作るB細胞が破壊されてしまう危険性があるのです。新型コロナワクチンとの関係を調べた研究も、すでに行われています。「コロナワクチンで、そんなことは起こっていない」と結論した研究もあるのですが、対象人数が極端に少なく、存在を否定したことにはなっていないようです。一方、「すでに起こっている」と結論した研究はいくつかあり、いずれも科学的な方法論に従ったものとなっています。ただし、直接的な証明にはまだ至っていません。この「敗者は抹殺せよ」理論は、ワクチンを受けた人ほど感染しやすいという事実を説明する上で説得力があり、記憶に留めておく必要があります。正確なメカニズムはまだ不明のため、研究の進展があれば直ちに当ホームページ(岡田博士HP)で取り上げるつもりです。
4.メッセンジャーRNAを包む膜に毒性がある
新型コロナワクチンの主成分であるメッセンジャーRNA(mRNA)は、脂質の膜に包まれた超微小な粒子となっています。「脂質微粒子」と呼ばれていますが、膜で包む理由は主に2つあります。ひとつは、mRNAが血液中を流れて行く途中で壊れないようにするため、もうひとつは、ヒトの細胞膜と融合して中に入り込みやすくするためです。このような膜は、ヒトの細胞膜や、コレステロールなどを包んでいる膜ともよく似ています。
新型コロナワクチンで使われている膜は、次の4つの成分からなっているとされます。
1 中性のリン脂質→ 外側が水になじみ、内側が水をはじく
2 コレステロール→ 微粒子の大きさを調整
3 ポリエチレングリコール(PEG)→ 微粒子どうしがくっつかないように
4 プラスの電気を帯びた脂質→ mRNAを抱え込む
米国の研究者が、脂質微粒子に対する反応をマウスで調べるという実験を行っています。mRNAを含まない、脂質微粒子の膜だけをマウスの鼻粘膜に与えて、反応を調べました。その結果、肺に激しい反応が起こり、すべてのマウスが死んだのだそうです(ただし人間に使うより多めの量でした)。
このとき、マウスを解剖して調べたところ、肺に激しい変化が起こっていて、白血球など「炎症細胞」が多数集まっていましたが、「免疫細胞」はむしろ減少していることがわかりました。脂質微粒子がもたらすのは、アレルギー反応ではなく、激しい炎症だったのです。
次に、脂質微粒子を含んだ溶液と、含まない溶液(プラセボ)を用意し、それぞれマウスの皮下に注射したところ、前者で激しい発赤と腫脹が認められました。さらに、4つの成分のうち「プラスの電気を帯びた脂質」を除いて脂質微粒子を合成し、同じ実験を行ったところ、皮膚の炎症はまったく起こりませんでした。脂質微粒子の膜には、強い毒性を発揮する物質が含まれていたことになります。このような動物実験は、ほかにも多数行われていて、即時に出る症状にはmRNAではなく脂質微粒子の膜そのものが毒性を発揮している、との結果で一致しています。
日本で新型コロナワクチンの最初の接種が医療関係者を中心に始まったころのことです。接種を受けた医師たちが、テレビのインタビューで「腕が腫れ、熱が出たが、免疫で体が守られている気がした」と口々に語っていました。実際は、免疫で守られていたのではなく、危険な炎症が起こっていたのです。この、あまりに微小な毒素は、免疫システムの監視網をすり抜けてしまうため、アレルギー反応も自己免疫疾患も起こしません。ワクチン接種の直後から2日以内に亡くなった方が大勢います。原因は、世間で言われているようなアナフィラキシー・ショックではなく、毒物による急性中毒だったと考えると、死に至る不可解な経緯など、すべての辻褄が合います。たとえて言えば青酸カリやフグ毒のようなものです(生体反応は異なる)。そのため、アナフィラキシーの特効薬とされるアドレナリン(商品名エピペン、ボスミンなど)を使っても命を救えなかったのです。